「リンゴ病(伝染性紅斑)の全国の患者数が、1医療機関あたり1.30人となり、過去10年間で最多になった」というニュースに、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか 。この数値は国立健康危機管理研究機構(JIHS)から報告されており、特に小さなお子さんを持つ保護者の方や、妊娠中の方にとっては気がかりな状況です 。
本記事では、このリンゴ病の流行について、その基本的な情報から、なぜ今これほどまでに患者数が増えているのか、そして私たち一人ひとりができる具体的な対策まで、専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。
この全国平均1.30人という数字は、あくまで平均値であり、地域によってはさらに深刻な状況が発生している可能性が考えられます。実際に、複数の県では既に「警報レベル」に達しているとの報告もあり 、地域ごとの注意喚起が重要性を増しています。また、今回の流行のピークが2025年の春頃と予測されている点は、リンゴ病が例年冬から初夏にかけて流行するパターンと一致していますが 、その規模が「過去10年で最多」であるという事実は、単なる季節的流行以上の要因が働いていることを示唆しています。
リンゴ病(伝染性紅斑)とは?基本を知ろう
リンゴ病は、正式には「伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)」と呼ばれるウイルス感染症です。原因となるのは「ヒトパルボウイルスB19(PVB19)」というウイルスで、主に子どもがかかりやすい病気として知られています 。
主な症状
リンゴ病の最も特徴的な症状は、その名の通り、両頬がリンゴのように赤くなる発疹です 。 この頬の発疹が現れる数日前には、微熱や鼻水、頭痛、倦怠感といった風邪に似た軽い症状が出ることがあります 。頬の発疹の数日後には、腕や脚、体幹にもレース編みや網目状に見える赤い発疹が広がることがあります 。この発疹はかゆみを伴うこともあり、日光に当たったり、体が温まったりすると一時的にぶり返すこともあります 。 大人の場合は、子どもと症状の出方が異なることがあります。特に成人女性では、発疹よりも関節痛や関節炎(手首、足首、膝など)が強く出ることが多く、発疹は典型的でなかったり、目立たなかったりすることもあります 。
感染経路
リンゴ病は主に、感染している人の咳やくしゃみなどに含まれるウイルスを吸い込むことによる「飛沫感染」と、ウイルスが付着したものに触れた手で口や鼻を触ることによる「接触感染」で広がります 。
潜伏期間と感染力のある期間
ウイルスに感染してから症状が出るまでの潜伏期間は、通常4日から15日程度です 。 非常に重要な点として、リンゴ病の感染力が最も強いのは、特徴的な頬の赤い発疹が現れる前の、風邪のような症状が出ている時期です 。この時期は血液中のウイルス量が多く(ウイルス血症)、周囲に感染を広げやすい状態にあります。頬に発疹が出た時点では、ウイルスの排出量は大幅に減少し、他人への感染力はほとんどなくなっているとされています 。
この「発疹が出る前に感染力がピークを迎える」という特徴は、リンゴ病の感染対策を難しくする一因です。症状がはっきりしない段階で無自覚のうちにウイルスを広げてしまう可能性があるため、発疹が出た人だけを隔離するといった対症療法だけでは、感染拡大の抑制効果が限定的になってしまうのです。
診断と一般的な経過
通常、リンゴ病の診断は特徴的な臨床症状、特に頬の赤い発疹に基づいて行われます 。特別な検査を必要としないことが多いですが、症状が典型的でない場合や、他の病気との区別が必要な場合には、血液検査でヒトパルボウイルスB19に対する抗体を調べることもあります。
多くの場合、リンゴ病は自然に治癒する病気であり、特別な治療薬はありません 。発熱や痒みに対して症状を和らげる対症療法が中心となります。一度感染すると、生涯にわたって免疫が得られ、基本的に再感染することはないとされています 。この生涯免疫の獲得は良い点ですが、裏を返せば、過去に感染したことがない人が多い集団では、大規模な流行が起こりやすいことを意味します。
表1:リンゴ病の症状と感染力の変化
| 時期 | 主な症状 | ウイルスの排出量 | 他者への感染力 |
|---|---|---|---|
| 潜伏期間 | なし | 低 | なし |
| 初期症状期 | 微熱・倦怠感・風邪様症状 | 高 | 最も高い |
| 発疹期(頬) | 顔面の紅斑 | 低下 | ほぼなし |
| 発疹期(体・四肢) | 体幹・四肢のレース様紅斑、かゆみを伴うことも | 低下 | ほぼなし |
この表からも分かるように、最も注意すべきは初期症状の段階です。
なぜ今、リンゴ病が大流行?考えられる3つの理由

国立健康危機管理研究機構(JIHS)や各自治体からの報告によると、2025年に入りリンゴ病の患者報告数が著しく増加し、多くの地域で警報レベルに達しています 。この急増の背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っていると考えられます。
理由1:ウイルスの流行サイクル
ヒトパルボウイルスB19による感染症は、おおよそ4年から6年の周期で流行を繰り返す傾向があることが知られています 。過去の日本における大きな流行としては、2007年、2011年、そして2015年が挙げられます 。現在の流行は、この自然な流行サイクルの一環である可能性が考えられます。つまり、前回の流行から時間が経過し、ウイルスに対する免疫を持たない人(特に子どもたち)の数が増加した結果、新たな流行の波が起きているというわけです。
理由2:コロナ禍明けの「免疫負債」
「免疫負債」という言葉を聞いたことがあるでしょうか 。これは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック期間中に、マスク着用、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保といった徹底した感染対策が行われた結果、インフルエンザやRSウイルス、そしてこのリンゴ病の原因ウイルスであるヒトパルボウイルスB19など、他の多くの一般的な感染症ウイルスの伝播も大幅に抑制された状況を指します。
その結果、特に幼い子どもたちが、例年であればこれらのウイルスに自然に曝露されて獲得するはずだった免疫を得る機会が減少しました 。そして今、COVID-19対策が緩和され、人々の社会活動が活発化するにつれて、これらのウイルスが免疫を持たない人々の間で急速に広がりやすくなっているのです。これはリンゴ病に限った話ではなく、手足口病やヘルパンギーナといった他の小児感染症も、コロナ禍後に患者数が増加する傾向が見られています 。
特に2025年の流行で4歳から5歳の子どもたちに患者報告が多いという事実は 、この免疫負債仮説を強く支持します。この年齢層の子どもたちは、人生の初期の数年間をパンデミック下で過ごし、通常の社会活動や他者との接触が制限されていたため、一般的な小児期感染症に対する免疫を獲得する機会が少なかったと考えられます。
理由3:社会活動の活発化と接触機会の増加
COVID-19に関する主要な行動制限が解除されたことに伴い、人々の交流、旅行、集団での活動が活発になっています 。これにより、ヒトパルボウイルスB19のような飛沫や接触で感染するウイルスが広がる機会が増加しています。特に、保育園や幼稚園、学校といった集団生活の場は、感染拡大の温床となりやすい環境です 。
これら「ウイルスの自然な流行サイクル」と「免疫負債」、そして「社会活動の活発化」という3つの要因が重なり合うことで、今回の「過去10年で最多」という異例の大規模な流行につながっている可能性が考えられます。いわば、自然な流行の波が、免疫を持たない人々の増加という土壌によって、より大きな波へと増幅されている状況と言えるかもしれません。
特に注意!リンゴ病のハイリスク群とは?
リンゴ病は多くの子どもにとっては比較的軽症で経過する病気ですが、特定の人々にとっては重篤な影響を及ぼす可能性があります。特に注意が必要なハイリスク群について解説します。
妊婦さん
最も注意が必要なのが妊婦さんです。過去にリンゴ病にかかったことがなく、免疫を持たない妊婦さんが感染すると、ウイルスが胎盤を通じて胎児に感染する可能性があります 。
その結果、胎児に重度の貧血や、全身に液体が溜まる「胎児水腫(たいじすいしゅ)」という深刻な状態を引き起こしたり、最悪の場合、流産や死産に至ることもあります 。このリスクは、特に妊娠初期から中期(妊娠20週頃まで)の感染で高いとされています 。ある調査では、日本人妊婦のヒトパルボウイルスB19に対する抗体保有率は20~50%と報告されており 、これは妊婦さんの半数以上が感受性を持つ(感染する可能性がある)ことを意味し、公衆衛生上の大きな懸念材料となります。
さらに注意すべきは、母親の感染が症状を伴わない「不顕性感染」であっても、胎児に影響が及ぶケースがあることです 。ある調査では、胎児感染が確認されたケースの約半数で、母親にはリンゴ病の症状が見られなかったと報告されています 。これは、妊婦さんが症状のある人だけを避けていれば安全というわけではないことを示しており、流行期にはより広範な注意が必要となります。
妊娠中の方や妊娠を計画している方で、リンゴ病の患者さんと接触があったり、リンゴ病を疑う症状が出たりした場合は、速やかにかかりつけの産婦人科医に相談することが極めて重要です 。
溶血性貧血の基礎疾患がある方
鎌状赤血球症や遺伝性球状赤血球症といった、赤血球が壊れやすい「溶血性貧血」の持病がある方がヒトパルボウイルスB19に感染すると、赤血球の産生が急激に低下する「無形成発作(アプラスティック・クライシス)」という重篤な状態に陥ることがあります 。これは命に関わることもあるため、厳重な注意が必要です。場合によっては、リンゴ病による無形成発作をきっかけに、それまで未診断だった基礎疾患の溶血性貧血が初めて見つかることもあります 。
免疫不全の方
HIV感染症の方、臓器移植後などで免疫抑制剤を使用している方、特定の抗がん剤治療を受けている方など、免疫機能が低下している方がヒトパルボウイルスB19に感染すると、ウイルスが体から排除されずに持続感染し、慢性的な貧血を引き起こすことがあります 。
リンゴ病の感染拡大を防ぐ!今日からできる予防と対策

リンゴ病には残念ながら有効なワクチンが存在しません。しかし、基本的な感染予防策を徹底することで、感染リスクを大幅に減らすことが可能です。
基本的な感染対策
- 手洗い: 最も重要かつ効果的な予防策です。石けんと流水で、手のひら、手の甲、指の間、爪、手首まで、最低15秒から30秒かけて丁寧に洗いましょう 。ヒトパルボウイルスB19は「ノンエンベロープウイルス」という種類のウイルスで、アルコールベースの手指消毒剤が効きにくいとされています。そのため、石けんによる物理的な洗い流しがより重要になります 。この点は、エンベロープウイルスである新型コロナウイルスの対策でアルコール消毒が推奨されたこととは異なるため、特に意識する必要があります。
- 咳エチケット: 咳やくしゃみをする際は、ティッシュやハンカチ、または服の袖や肘の内側で口と鼻をしっかりと覆いましょう 。使用したティッシュはすぐに蓋付きのゴミ箱に捨て、その後は手洗いを忘れずに行いましょう。
- マスク着用: 人混みや換気の悪い屋内、または自身が体調不良を感じる際には、マスクを着用することが飛沫の拡散防止に役立ちます 。
家庭内・地域社会での対策
- 個人用品の共有を避ける: コップ、食器、タオル、歯ブラシなどの個人用品は、家族間であっても共有しないようにしましょう。特に家庭内に体調不良者がいる場合は徹底が必要です 。
- こまめな換気: 室内の空気を定期的に入れ替えましょう。1時間に数回、数分程度窓を開けるなどして換気を行うことが推奨されます 。
- 体調が悪い時の対応: 自分自身やお子さんにリンゴ病を疑う症状(風邪のような症状、発疹など)が見られた場合は、無理をせず学校や仕事を休み、早めに医療機関を受診しましょう。特に周囲にハイリスク群の方がいる場合は、その旨を医師に伝えることが大切です。医療機関を受診する際は、事前に電話でリンゴ病の疑いがあることを伝えると、他の患者さんへの感染拡大防止に配慮した対応をしてもらえる場合があります 。
ハイリスク群を守るために
- 妊婦さんの場合: 最大限の注意が必要です。流行期には、可能な限り人混みを避け、風邪症状や発疹のある人(特に子ども)との接触を避けるよう心がけましょう 。家庭内にお子さんがいてリンゴ病に感染した場合は、妊婦さんはできるだけ濃厚接触を避け、手洗いやマスク着用などの感染対策をより一層徹底してください。可能であれば、流行期にはお子さんの保育園や幼稚園の送迎を他の家族に代わってもらう、病児の世話を他の家族が中心に行うなどの工夫も検討しましょう 。ただし、このような対策は、特に働く母親や核家族にとっては大きな負担となる場合もあり、社会全体の理解とサポートが求められます。
- 妊婦さんの周囲の方々へ: 妊婦さんのご家族や職場の同僚、友人の皆さんは、ご自身の健康管理と感染対策に普段以上に気を配り、万が一にも妊婦さんに感染させてしまうことのないよう、最大限の配慮をお願いします 。健康な人の行動が、社会全体の弱者を守ることに繋がります。
免疫力を高める生活
特定のウイルスに対する直接的な予防策ではありませんが、日頃からバランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、免疫力を維持することも、様々な感染症から身を守る上で大切です 。
表2:リンゴ病 予防策チェックリスト
| 予防策 | 具体的なポイント | 特に重要な人 |
|---|---|---|
| 正しい手洗い | 石鹸と流水で30秒以上、指の間や爪も念入りに | 全員 |
| 咳エチケット | 咳・くしゃみはティッシュや肘で覆う | 全員 |
| マスクの着用 | 人混み・換気の悪い室内、体調不良時 | 全員 |
| 個人の持ち物の共有回避 | タオル・食器・歯ブラシなどは個人専用に | 家族内・集団生活 |
| こまめな換気 | 1時間に数回、数分程度 | 室内環境 |
| 体調不良時の自宅療養 | 無理せず休み、必要なら医療機関に相談 | 全員 |
| 妊婦さんの周囲の配慮 | 感染源との接触を避ける手助け、自身の感染対策の徹底 | 妊婦本人・周囲の人 |
| ハイリスク者への配慮 | 免疫不全者や基礎疾患のある人への感染防止意識 | 全員 |
まとめ
現在、リンゴ病(伝染性紅斑)は過去10年間で最も多い患者報告数となっており、社会全体での警戒が必要です。多くの子どもにとっては軽症で済むことが多いこの病気も、妊婦さんや特定の持病を持つ方々にとっては深刻な事態を引き起こす可能性があります。
今回の流行の背景には、ウイルスの自然な流行周期に加え、コロナ禍を経たことによる「免疫負債」や社会活動の活発化が複合的に影響していると考えられます。
しかし、リンゴ病について正しく理解し、手洗いや咳エチケットといった基本的な感染対策を一人ひとりが徹底すること、そして特にハイリスク群の方々を守るための配慮を社会全体で共有することが、この流行の影響を最小限に食い止めるための最も有効な手段です。
もしリンゴ病を疑う症状が出た場合や、感染に関して不安な点がある場合は、自己判断せずに医療機関に相談しましょう。特にハイリスク群に該当する方や、そのご家族は、早期の対応が重要です。
私たち一人ひとりの意識と行動が、この感染症の拡大を防ぎ、大切な人々を守る力となります。
ぱくたそ[ https://www.pakutaso.com ]



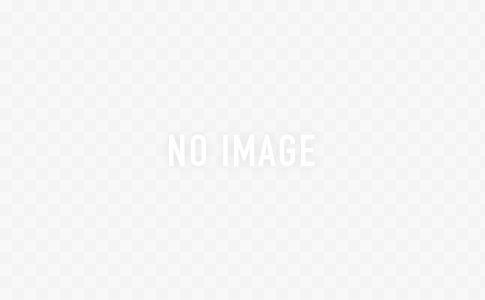







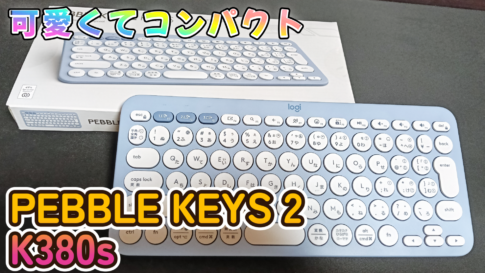




コメントを残す